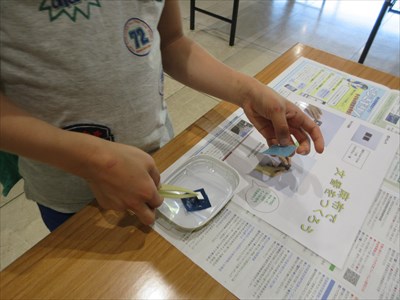現在開催中の企画展「外来生物」の関連行事である観察会「外来生物をさがそう!in 中央公園&鶴田沼」を2025年5月3日(土)に開催しました。前日の雨が嘘のような晴天となり、清々しいくらいの陽気の中、お子さんからご年配の方まで計30名が参加いただきました。

今回の観察会は生物系学芸員5名で、それぞれの分野の生き物について説明しました。
・植物担当:星学芸員
・昆虫担当:栗原学芸員
・無脊椎動物担当:南谷学芸員
・脊椎動物担当:小笠原学芸員
・菌類担当:山本学芸員
まずは中央公園での外来生物さがしから。玄関ポーチを出て中央公園に向かうと、早速ハルジオンやオッタチカタバミが見つかりました。どちらも外来生物です。星学芸員がハルジオンとそれによく似たヒメジョオンの違いや、オッタチカタバミと在来のカタバミの違いを説明しました。

さらに進んでいくと、シャガやヒマラヤスギ、園芸品種のシランなどがあり、そこで南谷学芸員から、分からない生き物を調べる方法の一つとしてスマートフォンのアプリであるGoogleレンズとバイオームの使い方について説明しました。どちらも種名の分からない生き物を調べるのに便利なアプリです。が、「正しいとは限らないので、それをヒントに図鑑等できちんと調べてください。それでも分からなければ、博物館で担当学芸員に聞いてください。」と補足しました。

中央公園の池の東側にはドバトが見つかり、小笠原学芸員が説明しました。ドバトはレーシ鳩や伝書鳩が野生化したハトのことです。

中央公園駐車場付近に行くと、モンシロチョウが飛んでました。これも外来生物です。
駐車場に植えてあるアキニレの見えるところで、栗原学芸員が特定外来生物のツヤハダゴマダラカミキリについて説明しました。「中央公園ではまだ見つかっていませんが、ツヤハダゴマダラカミキリはアキニレやトチノキを好むので、もしそういった樹木を見つけたらツヤハダゴマダラカミキリを探してみてください。」と言っていました。

駐車場から博物館に戻る途中、イセノナミマイマイを見つけました。大きなカタツムリで、「愛知県から兵庫県辺りに生息するが、なぜか中央公園にもいます。」と南谷学芸員。もう少し進むと、関東に生息しているヒタチマイマイが木の幹にいるのが見つかりました。

池のコイ(これも外来生物です)を見ながら博物館に戻り、博物館東側の草地や林アオスジアゲハやアブラナ、ハルシメジ、オカダンゴムシなどの様々な外来生物を見つけました。

ここまでが午前の部、午後は鶴田沼に向かいます。
鶴田沼では、駐車場近くの水路で南谷学芸員が見つけた外来生物のタイワンシジミ、アメリカザリガニ、クサガメを紹介しました。

ガビチョウ(外来生物)やキジ・ウグイス(在来生物)が鳴いていたり、ソメイヨシノ(外来生物)やカントウマムシグサ(在来生物)があったりといろいろな生き物が見られましたが、中央公園と比べると外来生物が少ないようでした。


最後には、参加者の皆さんがそれぞれ見つけた生き物を担当学芸員に聞いたりしながら、観察会を楽しんでいたようでした。参加者の皆さん、長時間の観察会、お疲れさまでした。
今回の観察会で見つけた生き物について、9/21(日)のとっておき講座(13時30分~、博物館講堂)で発表する予定ですので、こちらもぜひご参加ください。お待ちしてます。
現在博物館では
・企画展「外来生物~人によって運ばれた生き物たちからのメッセージ~」(~6/15まで)
関連行事:シンポジウム「栃木県の外来生物対策」(5/31(土)10時~16時 講堂)
学芸員による展示解説(6/8(日)14時~15時 企画展示室)
・テーマ展「地層の剥ぎ取り標本って、おもしろい!」(~6/15まで)
・テーマ展「とちぎ昔ばなし~弓の名手那須与一と九尾のきつね玉藻前~」(~6/15まで)
を開催していますので、ぜひご来館ください。
(自然課 三宅)